





最近の更新
このガイドは、日本焚火学会ができた1993年7月1日に発行されました。
当時焚火インストラクター選考委員長をされていた故・久保正登氏と、焚火インストラクターの角田寿氏ほかの執筆によるものです。
冊子として会員に配布されましたが、ここにそのまま掲載します。大変な力作で、資料的な価値も高いものですので、どうぞご参考に。
******************
高き屋に 登りてみれば 煙たつ
民の竈は 賑わいにけり
(仁徳天皇)
******************
日本焚火学会で用いる「焚火」とは、限られた空間で目的をもって焚物を焚くことである。「薪」とは、木を切るまたは折るなどして加工したもので、「焚木」は、未加工のものを含めた木の焚物の総称である。

火は人類に文明をもたらし、焚火は文化をもたらした。燃え上がる炎、集うものの心を一つにし、情熱と友情と希望を与えてくれる。
焚火を囲むすべての人々の心に通う安らぎは何であろう。父祖から受け継がれてきた本能的なものであろうか、それとも火を発見することによって今日の文明を築きあIヂてきた人類の、焚火の炎に対するいつまでも変わることのないノスタルジアなのか。
父祖代々燃えつづけてきた焚火、焚火文化。今その火は消えようとしている。われわれは−つの貴重な安らぎの手段を忘れようとしている。
焚火に関する記録は少ない。そこで田舎の先達の方々の協力を得、記憶の焚火文化を学び、父祖より多くの恩恵を授かった焚火をたたえる。
写真は、旧北村家住宅(川崎市立日本民家園のHPから)
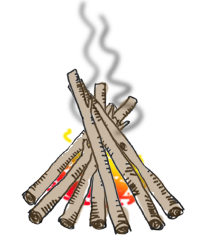
ビラミット型に薪を組み合わせる。

傘組み
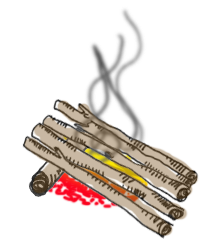
枕木または枕石を置きその上へ並列に薪を置く(枕組み)
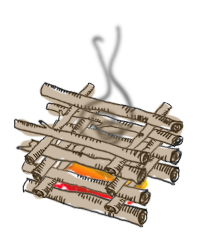
井の字型に組み合わせ、積み上げる(算木組み)
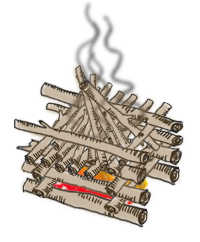
合掌型と井型との複合型
栗・杉(特に村物)
弾け音が強く、火の粉が飛散するので危険である
囲炉裏や火災のおそれのある場所では不適である
檜の葉・樅の葉・栂(つが)
一般的に雑木類の生木を燃やすと独特の匂いを発する。衣服に染みつき山林労務者では職業的体臭となる場合もある
槐(えんじゅ)の木・榧(かや)の木・松の葉
榧の匂いは不快なもので焚木として敬遠される
芯部が空洞のもの・・竹・ウツギ(トモシビ)・古木槙・ヌルデ・カマズミ(ゴウノミ)
竹は火力が強く風呂にくペるなといわれる
雑木は炎からオキ、次ぎに灰となる
朴(ほお)の木は炎からオキとならず灰となる
松は炎からオキとなり、灰とならず、オキが消えれば消し炭となる
松は肥えているため燃えやすいが、真っ黒いかがりを出す
朴・雑木類・樅・松・檜・栂・クロモジ
桐・ねむの木(コーカ)・栗・欅・樫・柿・クロキ・サンゴジュ(婆殺しと云われた)
アツマダの木・樫の葉・檜の葉
石や樹木に付着している白苔は水を吸っていない。強く握り締めると粉になるほど乾燥しているので火種には最適である。
立木の杉枝に付いているわずかな枯れ葉は、雨天でも風通しよく湿気が少ないので木登りして採取する。
濡れていても大きい枯れ木の芯部は乾燥しているので削って用いる。濡れていてもウダイカンバ(カバノキ科)はよく燃える。
肥松(松の根株)を採り小さく割る。
マッチが濡れているときは、まずマッチを肌で温めておき、鎌や鉈の柄を激しく擦りつけ摩擦熱を出しておいて、この部分にマッチを擦りつける。鎌や鉈の柄は樫や栗でできているので固い。
・ ボケの木を燃やすと茶釜が割れる
・ 柿の木を焚くと災難がくる。七代貧乏する
・ 桑の木で御飯は炊かれない
・ かずらの巻きついた木を焚くと難産する
・ 焚物の積み上げ高は家の経済力指標
・ 財を蓄え、火をつけるには、こもう、こもうにする
(割木を焚く家は身代がつぶれる)
・ 焚火の煙りは美男美女の方へ向かっていく
(煙る人をなぐさめる)
・ 野辺の煙りが向かうところへ次の不幸がある
・ 桐を焚けば鼠が増える
・ あつまんだに生木なし
・ コーカ(ねむの木)小枝なし
・ カッコウ(タンナサワフタギ)焚くより石焚くべ
・ 冬上夏下
(どうじょうかか=冬は上から、夏は下から火をつける)
古くから囲炉裏を囲み、オドロ・ホタを焚いて、一日の出来事を話し、客が来ると、ゴタゴタ煮立った茶釜のお茶とオキで焼いた芋・粟・餅などを焼き、ほのぼのとした温もりの中で明日のことを思ったものである。
焚火の材料としては、針葉樹、広葉樹いろいろとあるが、薪の小枝を折って焚いたのが常であったようである。割木は山里では数少ない収入源であり、特別の場合のみ焚いていたようである。
松は割木大束焚木としては燃えやすく、火力が柔らかではあるが、かがりが多く家の中・台所ではあまり使われず、火廻りが早いこともあって風呂などに使用された。
現代の陶磁器の工業生産品は重油バーナーや電熱を用いるが、エ芸品は冬場の水分が少なくなる時期に伐採したアカマツの薪を絶えず窯に投げこみながら長時間で焼きあげる。アカマツはテルペン類などの油を多く含み、火勢や火力が強い。
松炭はマクロ孔(仮導管)が大きく、急激に高温が得られる。鍛冶屋では鞴(ふいごう)炭として用いられていた。また、火付けの良さと、適当な時間で使い終わるという目的からカラマツ炭のバーベキューコンロも市販されている。
松の葉(コクバ)は杉の葉などとともに焚付け用として利用したり、漁師はタデ焚きにも利用していた。
肥松からは第二次大戦中のわが国では航空燃料や潤滑抽の自給を目的として、針葉油や樹脂からなる松根油を採ったものである。100年以上の松がよく、火付け用として最適であり、小さく割り切って囲炉裏・くどの横の燈台籠の中に入れて使用し、また、風呂場の明かりとしても使っていた。肥松はまた、追いこみ漁法で火振りにも用いた。肥松のかがり煤は上質墨となる。
マツ科の栂は古代修羅、近年木馬として使われた滑りのよい木である。
杉は焚木としては弾けが強く屋内、火災のおそれがあるところでは不適である。主に材木用として栽培される。コウヤマキは高級な庭木として植えられ、高野山に多いので名がついた。コウヤマキは水湿に強く、昔、棺として使われた。杉の葉を臼で粉にして香料を入れて作ったものが線香である。また、杉の木は屋根のソギふきに用いる。
檜は焚木としては燃えやすく、檜の葉はバチバチと音をたててよく燃える。法隆寺の西院伽藍は1300年を経た世界最古の木造建築であり、檜が使われていることは有名である。檜は防虫牲や耐腐朽牲・耐候性の点で優れている。檜の皮は神社の屋根などに使われる。
ヒノキ科の椹(さわち)は強度その他の点で檜に劣り、少し以前までは水湿に強いということから風呂の浴槽、ご飯を入れるお櫃などに使われていた。
榧(かや)は燃えるとさ不快な匂いを発する。将棋・碁盤に使われる。また、建築では床柱、縁板などに使われる.
その他槙・樅などが燃えやすい焚木となる。
広葉樹は焚木となるものが多く、薪として切り取り、幹は割り木(上木・中木)として売り物にした.上木は火持ちが良くオキとして残り火を使用、また木炭として良炭がとれた。ゴズ炭は一般の家庭ではアンカ・コタツに使用し、葉付きのオドロなどは焼いて灰とし田畑の肥料とした。農家では灰小屋があり、土壌改良に役立った。
桐は断熱性と弾性に富んでいて、桐ダンスは火事の勢いがよほど強くない限り表面が炭化して着火しにくく、収納品が焼けないといわれている。古く灰色になっている桐も一削りで白い肌が現れ、また凹みができても湯をかけると元に戻るという再現性がある。欠点として鉄分を嫌い容易に変色しやすく、桐建築では鉄釘を使わず、ウツギの木釘を使う。
樫は焚木としては燃えにくいが、炭としては楢(なら)と同様火持ちが良い。備長炭はウバメガシからつくられる樫炭で、鰻の蒲焼とか焼き鳥用に使われる。樫の葉は生でもよく燃える。樫は建築材としては高級品であり、その他船舶・車両材に使われる。
朴の木は焚木として燃えやすく、柔らかく細工しやすいので、下駄の歯(朴歯)をはじめ刀の鞘などに使われる。
槐(えんじゅ)の木は燃えにくく、匂いを発する。床柱などに使われる。槐花は止血薬に用いられる。
広葉樹の中には柾目や板目の美しいものが多く、木工細エに昔からよく使われる。例えば高扱な箱は本体は狂いの少ない桜、表面材は漆の乗りが良い梅、床脚は巧緻な彫刻に適すツゲというように用いられた。
広葉樹の中から様々な木炭がつくられている(樫物が主)。
ウバメガシ白炭。紀州木炭問屋,備中屋長右衛門に由来
櫟は上質の薪や炭材になるほか、上質の落葉を得るために植林されてきた。15〜20年ものが良い
コナラ。薪炭材のほか椎茸原木、建築などにつかう
灰をかけて消したもの
7〜10年の若い木を用いる。火力が強く、火持ちが良く、火相が美しい
炭材の粉末を硝石および硫黄の粉末と混ぜる。炭材として、ハンノキ、朴の木、桐、柳、クロウメモドキ、ヤマナラシなどが使われる
朴炭、静岡炭(駿河炭ニホンアブラキリ)、呂色炭(チシャノキ・アワセビ)、椿炭
炭材には柳のしなやかな小枝が主として使われる。ほかにも桑、ハンノキ、ミズキ、楓(かえで)などがある
草木としは、麻茎をオガラ炭としてカイロ灰に利用、稲藁は藁灰として火鉢に入れると炭の火持ちが良い。籾殻は焼いてスクモ炭として稲の菌床に敷き発芽を早めた

明治時代、山かせぎの村の分布をみると、薪を出していたのは太田川流域に沿う村々と高宮・沼田両郡に多く、そのほとんどは広島に運ばれ、炊事などに用いられた。
また広島城下には、宮島・能美島・倉橋島から多くの薪がきた。なかでも宮島は多く、明治30年の伐採禁止になるまでつづいた。薪を伐るために山子の制度があり、明治時代になって不況の折には、家数500軒の内、山子300人という数であった。都市への薪の供給は、昭和35年頃の都市ガスやプロパンの普及まで続き、その頃から山村人口の減少が目立ちはじめる。
太田川流域では、薪・炭が川舟・筏によって運ばれ、帰り荷には、塩や肥料(干鰯)などが積まれていた。
農村では、商い用として薪は冬の間に伐って用意しておいた。材料は松・槙・栗で、中でも槙が固くて火力が強く長く持つので、囲炉裏のオキにはよく用いた。松は槙に比べてやや火力・火持ちが弱かった。薪にほ30年くらいの木が一番よい。
長さ二尺五寸、径二尺のものを高さ六尺、幅六尺に並べたものを一坪という。大朝町の農家では自家用として、一年間に10坪必要であった。また下ゴリ(大きい木の間に生えている木を切ったもの)やオドロ(枝木)も束ねて積んでおく。オドロは一年に200束くらい使い、用意するのに一週間はかかった。
漁民は山を持たなかったが、農家の山林の枯枝・下草・落葉をとることを許されていた。
山を持たない農民は、山主が木を切る時に手伝いに行き、山の落葉をはかせてもらったり、また草刈りで鎌で切れる木は刈って燃料とすることが許された所もあった。
炭は商品として焼かれることが多かった。明治までは、安芸・備後の奥地は鉄がとれ、タタラに使われるタタラ炭や、タタラに付設された鍛冶屋が使うかじや炭などがたくさん焼かれた。鉄山師は、タタラに必要な燃料を得るために山林を買った。彼らのなかには大さな山林地主も少なくなかった。加計の佐々木(のち加計)家、島根県の田部・桜井家などである。明治時代にタタラが廃止になって、鉄山の山子たちは失業することになる。鉄山師は広い自山を利用し、家庭用木炭を焼いて、都市へ売りにだすことになる。山子たちはそのまま木炭の焼子になった。
黒炭は、木を二尺五寸の長さに切って立てて窯に火をつけ、口をふさぐ。はじめは濁って、ボタンの花のような煙が出る。そして、煙穴から出る煙が切れて、三、四日たつと、青い煙が出だす。次にロとショージ(煙出し穴)をふさいで、三、四日蒸し焼きにする。約一週間かかる。冷えた頃出す。
白炭は、ショージからの煙が切れると、濡れたものを頭にかぶり、ワラジを濡らして窯の口を開け、コグチまでひっばり出して、クロフクという黒い泥をトーシにかけてふるい、冷やしていく。白炭は三日くらいで出せる。
(資料 広島県史)